次は「さよならモルテン」です。
この楽曲には、最初から非常に深い意味が込められているような印象を受けました。
そのため、今回はしっかりと調べて深く考察してみたいと思います。
全力で取り組んでいきます。
アルバム『幻燈』のテーマと照らし合わせる部分です。
考えてみたいと思います。
やはり、これは「千と千尋の神隠し」的な視点で理解するのがしっくりくるように思います。
つまり、
旅に出る前のニルスと、旅を経て帰ってきたニルスという対比――
過去の弱い自分を捨て、新しい自分に生まれ変わるというテーマ
があるのではないでしょうか。
ニルスが小人になったこと、そしてモルテンと共に小人の世界で数々の経験を積み、
それによって自分自身が変化したこと――これらが象徴しているのは、
音楽を通じて自分が変化し、成長したというヨルシカ自身の表現
ではないかと感じます。
音楽による自己変革や成長の過程が、
この物語とリンクしているように思えるのです。
そして、ここからは、この物語に隠されているストーリーについてです。
実は、ここを重点的に取り上げたいです。
『ニルスのふしぎな旅』におけるスウェーデンの近代化とセルマ・ラーゲルレーヴの国家観
日本児童文学学会例会(プロジェクト人魚第14 回研究会)
中丸 禎子(東京理科大学: nakamart@rs.tus.ac.jp)
https://www7b.biglobe.ne.jp/~nakamaru_teiko/pdf/nils.2014.pdf
P5
「国民」の姿〈ニルス・ホルゲション〉
怠惰で愛を知らず、信心がなく、動物にも意地悪→勤勉で友情に篤い、「立派な国民」として帰宅
P5
ニルスを「尊敬すべき少年」にしたもの
・スウェーデンの地理と歴史
・ 動物とのふれあい・ケブネカイセのアッカの教え
・ ガチョウ番の少女オーサとの関わり
P5
〈オーサ〉
ニルスが小人になる前に、スコーネ地方で一緒にガチョウ番をしていたニルスと同い年の少女。ニルスと時を同じくして、弟のマッツとともにラップランドを目指して北上。複数回登場する唯一の人間。
…しかし、「ジプシーに、自分に親切にするものは自分と同じ病になる呪いをかけられた」とする旅の女を泊めた後、4 人の姉は女と同じ病気で死ぬ。親切が呪いで返される理不尽に耐えられなくなった父は家を出ていく。母、オーサ、マッツはスコーネに移り住むが、母も間もなく同じ病気で死去。オーサとマッツは、講習会でその病が結核であること、洗濯と掃除で予防できること、母と姉たちが病気になったのは呪いのせいではないことを知り、父に真実を告げるため、父がいるというラップランドを目指していた。
P6
〔引用4〕
事故〔引用者註:マッツの鉱山事故〕のあと、ニルスはなんとしてでも、ひとりぼっちになったガチョウ番のオーサを助けてあげたいと思い、奔走しましたが、父親が無事見つかると、オーサのためにすることもなくなり、それからは遠出もせずに、ガンたちといっしょに、ずっと山の谷間ですごしました。
そして、モルテンの背中にのって家へ帰り、もとの人間にもどれる日を待ちこがれるようになりました。オーサがふつうに口をきいてくれて、鼻先でドアをバンとしめられたりしない人間にもどりたいと思ったのです。(下、p.368)
P7
オーサはニルスとパラレルなルートで旅をするが、「大きく、りっぱになる」のではなく、「子どもにもどる」
これらの部分を引用しました。説明します。
弟マッツと一緒に父親を探していた姉オーサが、ひとりぼっちになったとき、ニルスが彼女を助けます。
オーサ自身は弟の葬儀が終わるまでは気丈に振る舞い、
大人たちとの交渉をこなしましたが、
葬儀が終わった後は泣き崩れてしまいました。
そして、その後に描かれる場面――
これが本当に、本当に重要なシーンだと僕は思います。
だからこそ、長文になりますが、ここで引用したいと思います。
【原作より引用】
セルマ・ラーゲルレーヴ 作
菱木 晃子 訳
P342
マッツの葬式がおわりました。
お客はみんな帰っていき、いま、小屋にいるのはオーサだけです。
オーサは、しっかりとドアをしめていました。ひとりで静かに、マッツのことを考えたかったのです。
マッツがいったこと、やったことが、つぎつぎと思いだされました。マッツのことを考えれば考えるほど、これからマッツなしで生きていくことが、どんなにむずかしいかが身にしみました。
やがて、オーサはテーブルに顔をふせ、声をだして泣きはじめました。
「マッツがいなくて、あたし、どうしてやっていけるっていうの……?」
P343
…ところがドアの前に立っていたのは、おとなの手のひらくらいの小さな小人でした。夜といっても外は白夜でまだ昼のように明るく、オーサにはそれがラップランドまでくるあいだになんども見かけた、あの小人だとわかりました。
小人を見ても、オーサは夢の中にいる気分でしたので、こわいとも思わず、おちついて立っていられました。小人に対して、マッツが父さんを見つけるのを助けてくれる人をよこすといっていたから待っていたのよ、と思ったくらいです。
それに、オーサの思ったことは、まちがってはいませんでした。小人は本当に、オーサの父親のことを伝えにきたからです。
小人はオーサが自分のことをこわがっていないとわかると、父親がいまどこにいて、どうやってそこへ行ったらいいかを、手短に話しました。
オーサは話を聞いているうちに、だんだんと頭がはっきりとしてきました。ききおわったときには、すっかり目が覚めていました。
すると急に、この世の者とは思えないものを相手にしていたことがおそろしくなって、ありがとうもいわずに小屋の中にひっこみ、ドアをバンとしめてしまいました。
説明します。
この場面は、
ヨルシカの楽曲「ノーチラス」のMVに描かれる場面と非常に似た印象を受けました。
エイミーを失ったエルマが桟橋まで辿り着き、
「ノーチラス」の詩が書かれた紙とギターケース、
そして泣いているエルマを「朝焼け」が照らすシーンは、
この場面と重なるように思えます。
つまり、
弟マッツがエイミーに、
姉オーサがエルマに当たり、
マッツの死後、オーサを救ったのが小人のニルスであるように、
エイミーの死後、エルマを救ったのは「ノーチラス」と「朝焼け」だった
のです。
「朝焼け」については、僕のブログ記事で詳しく書いているので、ぜひそちらもご覧ください。
さらに、マッツが亡くなった場所、
オーサが葬式をした場所、
そして小屋の中で泣き崩れたオーサがニルスと出会った場所――
これらはすべて『ラップランド』です。
そのため、
「ノーチラス」の歌詞にある“ラップランドの納屋の下”という表現が、
この「ニルスの不思議な旅」のこの場面を指していたと推測できます。
また、
アルバム『幻燈』のイラストに描かれている「さよならモルテン」の絵には、子供二人がガムラスタンの通りを走っている姿があります。
これが何を意味しているのか疑問に思っていましたが、
もしこれがマッツとオーサの姉弟を描いているとしたら、
その意図にも納得がいきます。
つまり、
マッツとオーサが父を捜してラップランドに向かっている場面
を描いているといえるのです。
これに考えが至った時、
あまりにも衝撃でしたので、
愕然としてしまいました。
はい、つぎは「いさな」です。
「いさな」は、小説『白鯨』をモチーフにしています。
ただ、この小説は読み進めるのが非常に難しかったというのが正直な感想です。
特に、物語の内容そのものというよりも、
登場人物や地名などカタカナ表記の名前が多すぎて、混乱してしまうことが多かったのです。
そして、論文を読んでも、その内容を掴むのが難しく、正直途方に暮れていました。
しかし、ようやく答えの手がかりを見つけた気がします。
これから、それを引用も交えながら整理してまとめてみたいと思います。
『白鯨』研究 ―物語世界と共鳴する音表現の諸相
濱田みゆき
https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/2000015
P18
『白鯨』に転じて考えるならば、イシュメールが語る物語を聴く「私(読み手)」と置き換えて、比較的容易に納得できることである。また、イシュメールが語り手としての姿を消し劇中劇の形がとられている場合であっても、私たちに語っていると考えれば、これはメタ物語世界的な空間に読み手が入り込んでいると考えることができるだろう。
P19
小説家は「物語内容を語らせるにあたって、『作中人物』の一人を選ぶか、それともその物語内容には登場しない語り手を選ぶか、という選択」(287)をすると述べ、語り手は登場人物として登場しない「異質物語世界の物語言説」と、登場人物が語り手となっている「等質物語世界の物語言説」の二つのタイプに分類している。そしてさらに、語り手が主人公である場合「自己物語世界」と定義している。『白鯨』は語り手イシュメールの「等質物語世界の物語言説」であるが、時にイシュメールは登場人物としては姿を消してしまう
P33
ここにもメルヴィルの事実と虚構を取り混ぜ、縦横無尽に織りなす創作方法をみることができる。
~
メルヴィルにとって、学術的な根拠や自分の航海からの情報を補足する捕鯨記などは、『白鯨』の物語を充実させるためのものであったといえる。まったくの創作ではなく、事実や捕鯨の物語を『白鯨』に取り入れることで、エイハブが立ち向かうモービィ・ディックの物語に真実味を与え、かつ、重厚感を与えている。
P34
先述のリンネの鯨は魚ではないとする説の否定など、メルヴィルは収集した情報を『白鯨』に適応させるために、虚実をミックスさせて書いていることがわかる。坂下のメルヴィルについての「航海の記事を先輩たちの著作からひっぱってくるのは彼の常套手段だった」(630)という指摘からも明らかなように、文献に書かれたことをまるで語り手の所見であるかのように書くなど、文献の利用方法は実に様々である。
P35
鯨を象徴的に絵画で描くことは、みる者に、鯨の真の躍動感や巨大さを伝える有効な手段ではあるが、実体を正確に伝えることはできないと書いているのである。第55章では、実際に鯨捕りが目にするような鯨の真の姿を、キャンバスなしで描くつもりであるとも言っている。これは、絵画ではなく、『白鯨』において言語で鯨の真の姿に迫りたいという語り手の意図であり、目指すところである。
~
語り手、ひいてはメルヴィルは、言語は実体を語るには不完全な道具であることを自覚していたが、それでも言語により鯨を表現したいという願望をもっていたということになる。
P36
鯨の姿形は記号として鯨を表しながらも、聖刻文字で覆われることによってその実体は読み解くことは出来ないものであることも象徴している。つまり恣意的な言語では表現することのできない自然の神的な象徴として、鯨を描いているのである。
P39
芸術家が美を達成した時には、美を人間に知覚させようとした象徴自体はほとんど無価値になっていると書かれた箇所を引用して、メルヴィルは、優れた書物は作者から独立し、それだけを鑑賞すればよいと述べている。
『白鯨』を読んでいる間、語り手であるイシュメールが主人公だと思っていました。
しかし、
中盤に差し掛かると、
突如として鯨に関する詳細な解説が始まり、物語の進行が薄れてしまいます。
さらに終盤では、
イシュメールの存在感がほとんどなくなり、代わりに船長エイハブが主人公のような役割を担うようになります。
物語の結末では、
白鯨との激しい戦いの末にエイハブが海の中で命を落とし、生き残ったのはイシュメールただ一人でした。
この物語が『幻燈』とどのように関わってくるのかを考えると、
「神のような幻想を描く」
というテーマが共通しているのではないかと思います。
『白鯨』において、
白鯨は神のような存在として描かれ、
人間である船長エイハブがその神に挑む形となっています。
時代背景について論文を読む中で分かったことですが、
当時、鯨に関する情報はほとんどなく、
存在していても本に書かれた文字や記号のような断片的なものに過ぎなかったようです。
そのため、
作者のメルヴィルは『白鯨』を何度も書き直す際に、
鯨に関する文献を丹念に集めて執筆に取り組んだといいます。
それでもなお、最終的には未完成の形で終わったようです。
これほどまでに、
鯨、つまり白鯨を文字で表現することがいかに難しいかが、
この作品の根底にあると言えます。
『幻燈』に話を戻すと、
「いさな」の楽曲に描かれている絵は、
女性がソファーで横たわり眠っている姿です。
一見、部屋の中にいるように見えますが、その周囲はまるで海の中のように描かれています。
この『幻燈』のストーリーは、
画家である男が実在しない幻想の女性を描こうとしている物語だと、
「いさな」の楽曲を通じて語られているように感じました。
そのため、MV「第一夜」では男女が描かれている場面が登場しますが、最後には男性がキャンバスの中へと吸い込まれていきます。
ここで気づくべきだったのかもしれませんが、
この物語において、
女性は最初から存在していないという前提でMVを解釈しなければならなかった
のだと思います。
今世では出会っていないのかもしれません。
実在しない女性でありながら、彼女が頭の中の幻想として存在している。
それゆえに、その姿をキャンバスに描いているという点が、
『幻燈』のストーリーと深く関わっているのではないかと感じました。
そして、これは補足でありますが、
どれほど伝わるかは分かりませんが、あえて書かせていただきます。
『白鯨』研究 ―物語世界と共鳴する音表現の諸相
濱田みゆき
https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/2000015
P20
メルヴィルが義父レミュエル・ショー(Lemuel Shaw)に1849年10月6日付で宛てた手紙には、『ホワイト・ジャケット』と『レッドバーン』の二つの作品について次のように書いている。
They are twojobs, which I havedone for money-being forced to it, as other men are to sawing wood. And while I have felt obliged to refrain from writing the kind of book I would wish to; yet, in writing these two books, I have not repressed myself much ― so far as theyare concerned; but have spoken pretty much as I feel. ―― Being books, then, written in this way, my only desire for their “success”(as it is called) springs from my pocket, & not from my heart.(Leyda 316)
この手紙からは、三つのことを読み取ることができる。
一つ目が、メルヴィルは生活の糧を得るためにこれら2作品を書いたということ。
二つ目が、売れる作品を書くために、メルヴィルは執筆時から読者である大衆を想定して書いたということ。
そして三つ目が大衆向けに書いた作品で、自分の望んでいるような内容の本を書くことは控えたが、一方で自分の書きたいことを抑えてはいないということである。
三つ目のことは少しわかりにくいが、メルヴィルは大衆向けの内容にしたが、その書かれた内容については自分の思う通りに書いているということであろう。
この部分については細かく言及を控えますが、
ヨルシカはどうしてこんなにもわかりづらいのかと思うと、
なんだか泣きそうになりました。
たとえ誤解を生むような表現であったとしても、
また、多くの人がメルヴィルの手紙というエピソードを知らないとしても、
言葉で詳しく説明しようとしなかったことに対して、申し訳なさを感じました。
僕らに教養が足りなかったのだと。
なんか、本当に申し訳ないです。
はい、いよいよ終盤ですね。
次のテーマは「左右盲」です。
このテーマについては、チノカテとの考察もありますので、ぜひそちらもご覧ください。
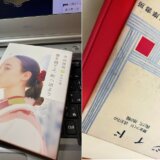
それでも、やはり改めて自分自身の視点で考えてみる価値があると思います。
この論文を読んで、「幸福な王子」という作品に「唯美主義」というテーマが込められていることを初めて知りました。
それまで私は、この物語については自己犠牲の意味合いがあるとしか考えておらず、
むしろそれが唯一のメッセージだと思い込んでいました。
さらに、
自己犠牲による善行の結果として、幸福な王子は天国に近しい場所へ行き、生まれ変わる機会、
つまり転生をすることができた、という解釈に基づいて作品を理解していました。
それでは、こちらの論文を読んでみてください。
オスカー・ワイルド「幸福な王子」 ――唯美主義運動の〈使者〉としてのツバメ――
輪湖美帆
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6812
P3
このようにツバメは、芸術を生活の中に取り入れていこうとした唯美主義運動において一つの重要なモチーフであったことがわかる。
P5
美しさと実用性という二つの価値がこのテクストのキー概念となっており、ツバメも初めはその二つは一致しているべき、という考え方を共有しているのである。
P5
ツバメが王子という「芸術作品」の声を聞くことのできる唯一の存在であり、その *musical voiceʼ (Wilde, Works 30) に従い、貧しい人々に王子のサファイアやルビー、金箔を届けていることが大きな意味を持つことになる。
P9
すなわち「幸福な王子」においてもまた、〈表層〉から〈内実〉を解釈する行為がいかに傲慢で的外れかが、強調されているように思われる。
P10
しかしまたしても注意しなくてはならないのは、アンデルセンの結末では天使たちと花は一緒に歌っているのに対し、ツバメと王子は、天国では別々になっている点である。すなわちツバメは楽園の庭(*my garden of radiseʼ) に、幸福の王子は黄金の街(*my city of goldʼ) に行くと書かれており(Wilde, Works 35)、ごみの山で共にいた二人は、天国で一緒になることはなく、ここでも、ラスキン的唯美主義は完全には達成されないようでもある。
P12
したがってワイルドの「幸福な王子」は、英国の唯美主義および唯美主義運動を、〈表層〉だけが流通し、〈内実〉は理解されないという、それらが陥りかねない問題点を見せつつ描いた上で、一般家庭へと発信されている。その意味で唯美主義運動の〈使者〉としてのツバメのような作品と言えるかもしれない。
そこで、「唯美主義」とは何なのか。ChatGPTに聞いてみました。
唯美主義とは、芸術や美そのものを追求し、道徳や実用性といった他の価値観から独立した美的価値を最優先する思想です。
この考え方は19世紀後半に広まり、「芸術のための芸術(Art for Art’s Sake)」というスローガンに象徴されます。
オスカー・ワイルドなどが代表的な人物で、美の独立性や感覚的な喜びを重視し、形式美を高く評価しました。
唯美主義は、芸術の存在意義を問い直すとともに、人々に純粋な美の体験をもたらしました。
それでは、「唯美主義」がどのような意味を与えているのかについて、他の論文も読んだ内容を自分なりに考えてみます。
当時の時代背景では、
作品や物に対して「美しさ」と
「有用性」の両方が重んじられ、
それによって価値が決められていました。
しかし、
唯美主義の思想は「有用性」の無い作品でも、
「美しさ」があればそれのみで価値がある
と主張するものです。
僕も、このような理解で捉えています。
この視点を踏まえ、「幻燈」においてヨルシカが「幸福な王子」をテーマに選んだ意図を考えてみました。
これはヨルシカだけに限らないことかもしれませんが、
自ら生み出した作品、
つまり創作物そのものについて、
外面的な要素(アウトライン)は伝わるものの、
その内面的な本質(コンセプト)までは完全には伝わらない、
というもどかしさがある、
それを表現しているのではないでしょうか。
「幸福な王子」のストーリーでは、
王子が自身の宝石や金箔を貧しい人々に渡すことで一時的に幸福を与えるものの、
その行為は根本的な問題解決には繋がりません。
これを創作に置き換えると、
創作物を届けることにより評価を得られたとしても、
その本質的な思いや意図が相手に完全には伝わらないことへの苦悩を示しているように思います。
さらに、「左右盲」の歌詞には「だんだんと忘れていく」というニュアンスが込められています。
創作活動の時間は経過していくと、
受け手つまりリスナーにどんな作品を届けるべきか、
どんな作品を届けていっていたのかが分からなくなり、
次第に自分の頭の中で描いた幻想がそのまま創作物へとなっていく
――そういったニュアンスがあるのかなと思いました。
そういう風に妄想を膨らませていると、
送り手の意図を完全には読み取ることができないかもしれません。
それでも、
受け手としては作品に対して真摯に向き合いたいという気持ちが強くなりました。
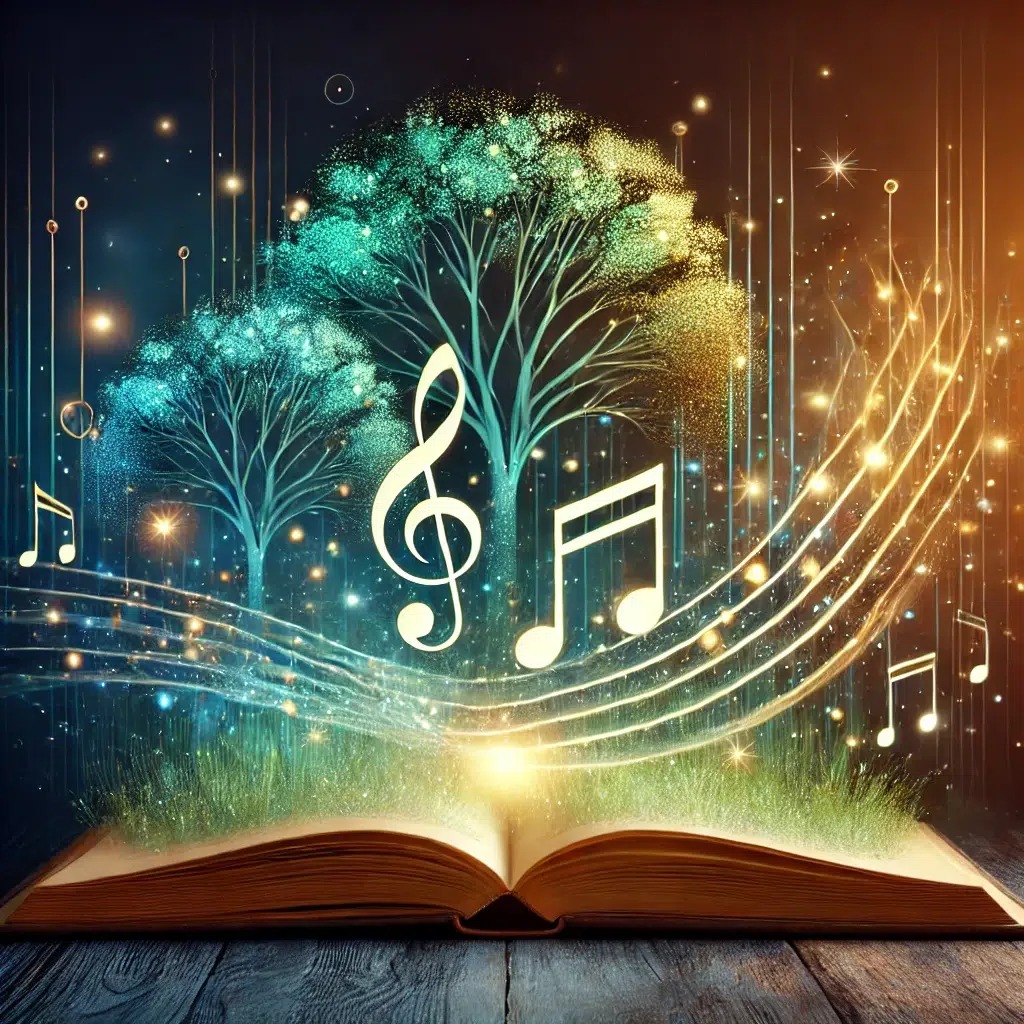 音楽と考察の森 ”Groval of Global”
音楽と考察の森 ”Groval of Global” 


