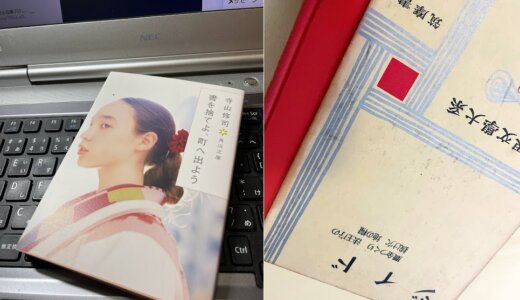次はチノカテです。
『チノカテ』については、以前ブログ記事にも書きました。
そのときは、本である『地の糧』と楽曲『チノカテ』について考察をまとめていたと思います。
実際に『地の糧』を読みながら、うんうん唸りつつ書いた記憶があります。
ところで、
『地の糧』は読めましたか?文庫本として発売され、ニュースにもなっていましたね。
僕も何とか読み終えましたが、
Twitterでは「文庫本を買った」というツイートをよく見かけた一方、
その後音沙汰がない人も多いようで……
ああ、途中で散っていったのかな、
とか思ってしまいました。
そして、
この時点で書く際にポイントとなるのは、
「月猫」のライブです。
このライブはYouTubeで全編公開されていますが、
その中に『地の糧』の要素が表現されているように感じました。
創作における主観と客観、
画家と動物がそれぞれ何を意味しているのか、
さらにあの朗読劇で描きたかったものが何だったのか、
……これらの問いに対して、『チノカテ』という楽曲を解釈することで答えが見えてくるのではないかと思いました。
ただし、これらのテーマを深掘りするのは非常に難解でもあります。
そこで、自分が注目したいと感じたポイントを補うために、ある文献から引用を行います。
解釈はゆっくりしていきたいと思います。
(成谷麻理子 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) 2008-10-10)
P6
主観が、純粋な認識主観となること-、即ち徹底した観照の境地にこそ芸術の域があるとするこの境地は、鏡に映った像の、主体認識が消えるということである。凝視し、表れてくるのは第三の芸術の域である。しかし一方が一方の眼差しに応えているうちに、どちらが主体なのか、主体は自己の存在を脅かされ、そこには不安や懐疑が生じる。主観と客観を分けるという概念、対象物に対して働く主体の意識は、認識主体への疑念となる。
P7
ジッドがアフリカの大地で見た朝焼けや、 360度に広がった風の通る空、土地の人々の邪気の無い振舞いは、ジッドの内に潜在する自意識を超えた生命の力を呼び戻した。それは絶望の中でこそ知る生の法悦であった。
P9
聖書や教会で教わった「神」に、暗闇で坊往うジッドは救われることはなかった。また理論や知が救うこともなかった。あらゆる定義がその形を崩し、形を成さず、捉えることのできないものの中にこそ彼は新たに信ずるものを見出したのだった。それは圧倒的な自然や、絶望の中で息づく実感を肯定することによって知る「生」の姿であった。
P10
ここで改めて「ナタナエルとは何者であったのか」という問いが想起される。 「私」やメナルクによって導かれる存在であり、常に「私」が語りかける存在-。それは、 「私」が自分の声を伝え愛する存在であり、 「私」がジッドであるならば、語りかけるナタナエルもジッド自身ではなかったのだろうか-。主客の分離と生の絶望に『地の糧』の元がある。…。 「私」は「私」でありながらナタナエルであり、客観された「私」である。だがこの両者はもはや鏡に映った対面像ではなく、眺める側と眺められる側との一致が成されている。
あと、ジャケットについてです。
ヨルシカの「チノカテ」のシングルジャケットを見ながら、
どの部分が『地の糧』に関連しているのか、ずっと考えていました。
そんな中、この論文を読んでいると、
アンドレ・ジッドの自伝的小説『一粒の麦もし死なずば』に関連する記述が目に留まりました。
おそらく、
この題名のイメージがジャケットにも込められているのではないかと思いました。
『一粒の麦もし死なずば』という題名は、
新約聖書『ヨハネによる福音書』第12章24節の言葉に由来しています。
「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。
しかし、
もし死ねば、豊かな実を結びます」
という意味で、
そこから導き出されるのは、
「地の糧」とは一粒の麦として地に落ち、死んで糧となることで他者に影響を与える存在になる、
という解釈です。
つまり、
これは自己犠牲や自己変革を通じて、
新たな価値や成果を生み出すことを象徴しているのだと思います。
自身の終わりが、また新しい自身だったり他者への影響を与えるといったことが「チノカテ」にそのようなテーマを内包させているように感じます。
次は「雪国」です。
「雪国」も「夏の肖像」と同様、まだ配信されていない楽曲です。
そして、この楽曲のモチーフは題名そのまま、川端康成の小説『雪国』です。
関係ありませんが、あのカクテルは好きです。
この楽曲はライブで演奏されてますので、ぜひご一覧をお願いします。
『雪国』のストーリーは、主人公の男(島村)が都会から越後湯沢へ旅行をするところから始まります。
島村には妻がいるのですが、一人でこの地を訪れ、旅館で休暇を過ごします。
この物語の終盤までの展開は、特段珍しいものではないかもしれません。
しかし、
随所に挿入される情景描写や登場人物の所作は非常に繊細で、
文章から古き良き「和」の美しさを感じ取ることができます。
この点が、『雪国』を特別な作品たらしめているのだと感じました。
と、思ってました。
このように書いてみましたが、
川端康成の『雪国』という作品の核心とは何か、
改めて調べた上でまとめようと思いました。
その過程で、「鏡」のなかの世界という言葉にたびたび出会いました。
評論や考察、さらには論文のような形式で書かれた文献の中に登場しており、
非常に興味深かったため、ぜひ参考にしたいと思い読み進めました。
実は、「鏡の世界」に注目したのは、少し前にヨルシカがX(旧Twitter)で投稿していた言葉を思い出したからです。
この「鏡」というキーワードが、『雪国』とヨルシカの楽曲をつなぐ重要な手がかりになるのではないかと考えています。
こちらは、ヨルシカのライブ「月と猫のダンス」の脚本に関する言及です。
「月と猫のダンスの脚本は、自分の創作の変遷を隠喩的に表した構造をしている。鏡に映る姿を見て初めて自分がどういう形か知る、というのはヨルシカの物語に共通する要素の一つで、鏡はそのまま客観視という言葉に言い換えられる。自分にとって新しいものを描いていたつもりでも、大抵が、結局自分自身を抜け出せていない。そうして鏡を見ると、いつか描いたあの絵に良く似た、奇妙な姿をした自分が見える。これはそういう話です。」
(2024年9月28日 以下のXのポストより)
ヨルシカの物語において、
「鏡」を通じた自己の客観視、
そして自分自身を抜け出せないというテーマは、
一体何を意味しているのでしょうか。
このテーマが、
川端康成の『雪国』を調べていく中で出てきた「鏡」の中の世界とどのように関わってくるのかが、非
常に気になります。
だからこそ、
『雪国』の考察を進めるうえで、
「鏡」なかのの世界という概念
をさらに詳しく掘り下げていこうと思います。
このテーマを探求することで、
『雪国』とヨルシカの楽曲「雪国」が共有する深層を浮かび上がらせることができるのではないでしょうか。
〈論文〉川端康成 『雪國』 読解試論―「鏡」の世界をめぐって―
2014-06-16 河村民部
P65
創作とは、いわば、非現実の視線でもって、現実世界を映し出す試みである…。映し出された世界は、したがって、非現実の、鏡のなかの様相を帯びるに至る。この創作の非現実の眼の作用を、写された現実世界が破り、存続不能にするまでになると、創作者は、己の作り出した世界を立ち退くことを余儀なくされる。
P65
日頃から空想・非現実の世界に生きている人間は、自分で空想・非現実の世界だと思うところに来て、はじめて、逆に現実を思い知らされる。~トンネルを抜けた世界こそが、空想・非現実の世界ではなく、逆に現実の世界であり、主人公はそれを思い知らされる。
P67
曇りガラスに突然出現したのは病人を看病する葉子の眼であるが、この葉子という女が、このようにして鏡を媒体にして、島村の想像世界では、駒子と二重写しとなって姿を現すことから物語が始まるところが、川端の小説家としての天才を証拠立てている。
P76
このように「自然のもの」である「鏡」のなかの世界が島村の「急所」にあって、もう一つ別の「人口のもの」の世界、つまり意識の世界がある。放心状態から我に立ち返った時の島村は、後者の世界の住人となる。島村は、いわば、このように「自然」の世界〈無意識の世界〉と「人口」の世界」〈意識の世界〉を往来している。
P96
このとき島村が思い出すのは、列車の中で葉子の顔に野山の火が灯ったときのことで、この葉子の眼に灯る火を思い出すたびに、島村はそこに重ねられてきた駒子との歳月を二重写しにして見てきたが、この瞬間にも葉子と駒子は島村の心の鏡の中で、二重写しになって再現される。そしてまた「なにかせつない苦痛と悲哀」が再び意識に上る。
P97
こうして作者は、駒子と島村の再生への予兆を示唆して物語を閉じているように思える。
このような部分を「雪國」読解試論から引用させていただきました。
『雪国』の序盤では、二人の女性を描いた文章の中で「鏡」のような表現が使われています。
この「鏡の中の世界」は非現実のものであり、
物語の中では主人公の島村にとって、
雪国という町や二人の女性(駒子と葉子)が
まさにその非現実の世界に属しているかのように捉えられています。
島村は、あえてそれらを非現実的な存在として見ることで、現実から距離を取ろうとしているのです。
しかし、
たとえそのような視点で非現実の世界を見ていたとしても、
島村は雪国で生活する人々やその息遣いに触れることで、否応なく現実を突きつけられる瞬間を迎えます。
この解釈は、島村だけでなく川端康成自身の視点とも重なる部分があるように思います。
つまり、
『雪国』における「鏡の中の世界」とは、
現実と非現実が交錯する場所であり、
非現実の中に身を置きながらも、
最終的には現実世界を意識させられる場
として機能しているのです。
さて、
このような点を踏まえて、
ヨルシカの「雪国」を見てみると、
ありますよね。歌詞に。
この部分です。
僕の躊躇いが 月に被さってまるで海の底ね ぼうと座って水面に映った僕らを見ている
貴方の涙 風に舞い散ってまるで春の中ね ぼうと座ってスープに映った僕らを見ている
~
ヨルシカ 「雪国」より引用
はっきりと言いますが、
ヨルシカが「雪国」の楽曲としてこの歌詞を入れ込んでいることから、
間違いなく
「鏡の中の世界」を念頭に置いて作られていると感じます。
この歌詞に登場する「水面」と「スープ」は、
どちらも「鏡」の性質を持っており、
それぞれの中の世界を外側にいる僕らが見ているという構造になっています。
ここでのポイントは、
「鏡の中の世界」は自分にとって非現実なものと認識される一方で、
実際にはそこに映し出されているのは自分自身であり、
むしろそれが現実そのものだということに気づかされる点です。
この認識の転換が、『雪国』における「鏡」と通じる部分であり、
それをこの楽曲に巧妙に落とし込んでいるのではないでしょうか。
ここまで、強く述べているのは、
やはりライブ「月と猫のダンス」を観たからかなあと思います。
また、「雪国」の歌詞に登場する「ぼうと」という言葉には、
単に「ぼーっとしている」という意味だけでなく、
川端康成の『雪国』をモチーフにしている点から、
炎が音を立てている「ぼうっと」という意味も込められているのではないかと思いました。
『雪国』のクライマックスでは、炎が情景の中で重要な役割を果たしています。
この楽曲における「ぼうと」という表現も、
非現実的な心情を表すと同時に、
炎の揺らめきや音を象徴的に取り込むことで、
文学作品と楽曲のつながりを強く意識させるものになっているのではないでしょうか。
次は、「月に吠える」についてです。
この曲は、私にとって非常に暗い印象が強く、
なぜかシングルリリース配信があった後もブログ記事に書くことができず、
ずっと避けていました。
それほどまでに、どこか心の中で距離を置いていた作品です。
とはいえ、正直なところ、曲の内容についてはほとんど知りませんでした。
いわば、食わず嫌いならぬ「読まず嫌い」とでも言うべき感覚を抱いていた楽曲が、
この「月に吠える」でした。
そして、さまざまな資料を読んでみましたが、萩原朔太郎という人物をとらえるのは非常に難しく感じました。
そのため、自分なりの解釈を深めるよりも、表現について言及している論文の引用が中心になりそうです。
この点については申し訳ありませんが、引用を通じて彼の本質に迫っていければと思います。
萩原朔太郎「月に吠える」の思想と方法
長野隆
https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/records/2026
P41
「精神」の飛躍=〈無限〉というが、人間の〈有限〉と〈断絶〉を規定しているかに見える当の「肉体」こそ、実は最も現実的な形で〈無限〉を所有しているのである。つまり、「生命」の〈連続〉、結合として。
P4
「月に吠える」―といより萩原朔太郎の詩の核心は、彼もいうように“疾患時代”の作品がすべてである。詩人は、それらの形象を得るために、みずから進んで病いの下に身を伏せていたにちがいない。
P13
真理とは五感の上に建てられたる第六感の意義である。いやしくも五感以外の方法、たとえば考察や瞑想や空想によって神秘を感触したと称するものがあれば、それは詐欺師であるか狂人であるかの一つである。…詩とは五官及び感情の上に立つ空間の科学である。
P24
萩原朔太郎一個体の演ずる“愛”の生体ドラマは、すべからく「生」=「生命」の〈再生〉に収斂していく道すじを辿っているように見える。「卵」や「種」に己れを仮託せんとするモチーフは、その“孤独”がみずから探り出した結論=象徴であり、また「母体」や「大地」に自身を見立てねばならぬ意味は、彼の“愛”なるものが方途もなく自閉したまま、ほとんど「自然」のレベルにまで突き詰められ拡大されていた事実を明かしている。
P25
自分は神と接触せんとして反発される、自分は物象と接触せんとして反発される。自分は恋人と接触せんとして反発される。その反発の結果は,何時も何時も、我と我とが固く接触する。接触の所産は詩である。
~他への“愛”とは、結局“自愛的”に拠りどころを求めるしかないという身体=個体の宿命を、萩原はみずからに教えさとしているのである。~地に落ちた一粒の「種」,掌の上に乗せた孤独の「卵」に見入っていた詩人は、このときようやく“愛”という真理の核心に手が届いたのだ。
P27
一粒の麦、地に落ちて死なずば、唯一つにて在らん、もし死なば、多くの果を結ぶべし(ヨハネ伝12・24
一粒の麦(=種)は「卵」に見立てられるし、「果」が〈再生〉=〈復活〉を暗示しているのは言うまでもない。ここでの「死」は「生命」の中絶を意味せず、他の大いなる「生命」に飲み込まれる〈仮死〉を暗示させているのだ。物理的な意味で言えば一粒の種の「死」とは腐敗や風化、―即ち消滅―を指すだろうが、バイブルの暗喩は、「大地」という「生命」に吞み込まれ抱かれる〈仮死〉を想定させており、その上に築かれる「生」の完成―即ち〈再生〉―を示唆している。つまりこの寓喩の描く構図は、「大地」=「母胎」の中に落ちた一つの「種」=「卵」〈受精卵〉による〈仮死〉と〈再生〉のドラマなのである。
P35
〈仮死〉の実現とは〈再生〉の予告であったはずである。丁度「腐敗」が新たね「生」の繁殖の場であるように、復活は死をもって為し了える。~本当の「死」のドラマは、そのあとに起る。「腐敗」こそ「死」のもっとも本質的な意味―「死」の恐ろしさと、そこに共生する“生の繁殖”をドラマティックに演出するものである。〈新生〉はまさに「腐敗」に従属しているのだ。
P38
…自然が生理にしか視えなくなった詩人が、そこで何かを視ようとする―‐実感的に掴もうとするーーと、いきおい自然生理の根源、即ちそのつじつまを視てしまうというような逆立ちしたリアリズムについてである。~つまり“幻想”をつくり出しているのである。ここにあるのは“像自体、”像でしかあらわしようのない「生理」である。形の定らない生理、身体の輪郭を喪った官能いうものが、逆に“像”を通して実感を取り戻しているような詩人の現状である。
疾患による自身の身体の異変や悪化を「腐敗」や「死」と捉え、
そこからの「再生」を幻想として描き出し、
それを詩で表現したのでしょう。
この「再生」というテーマは、
実際に「腐敗」という状態を体感した上で
初めて生じるものです。
そのため、
「腐敗」の過程から芽生えるイメージが、
詩の中では竹を通じて
象徴的に表現されているのだと感じました。
また、この文献は本考察の理解を深める助けになるかと思いますので、
ぜひ一読してみてください。
病床生活からの一発見(萩原朔太郎)
青空文庫リンク
萩原朔太郎の表現が、ヨルシカの楽曲や歌詞の随所に影響を与えているように感じられます。
例えば、
「五月は花緑青の窓辺から」という楽曲がありますが、
このタイトルや歌詞の持つ詩的なニュアンスは、
朔太郎の詩作に通じるものがあります。
この関連性について、このサイトを見てはっとさせられる部分がありました。(雲雀料理という萩原朔太郎の作品についてです)
さらに、ナブナさんがよく使う「喩える」という表現も、
萩原朔太郎の影響をうかがわせます。
萩原朔太郎についての論文を読んでいる中でも、
比喩表現について何度も強調されて箇所が多くありました。
ナブナさんの楽曲に見られる豊かな比喩も、
この芸術的なアプローチを受け継いでいるのではないかと感じました。
次は、レイ・ブラッドベリの『華氏451度』についてです。
なぜ、この小説がヨルシカの楽曲『451』の題材として選ばれたのか。
その理由を探るために考察を進めていきます。
『華氏451度』に関する論文や学術的な分析が少ないことから、
物語の感想を中心に展開しつつ、
小説を読んでいる中で
「ここがヨルシカとリンクしているのでは」
と感じた部分を抜粋してお伝えしていきたいと思います。
①華氏451度 [新訳版]
著者 レイ・ブラッドベリ
訳者 伊藤典夫
発行所 株式会社早川書房
P235
太陽は毎日、燃えている。太陽は、“時間”を燃やしている。世界は円を描いて猛進し、軸回転し、時間は年月と人々を燃やすのに忙しい。おれがなんの手助けをしなくとも、その営みはつづく。だからおれがほかの昇火士といっしょになってものを燃やし、太陽が“時間”を燃やしていたら、なにもかもが燃えることになってしまうではないか! だとしたら誰かが燃やすのをやめなければならない。太陽がやめるはずはない。・・・誰かが、本でもレコードでも頭のなかでもいい、なんらかのかたちで保存し、保管していかねばならない。・・・世界は、ありとあらゆる種類、ありとあらゆる規模の燃焼だらけだ。
この部分は、ヨルシカのアルバム『幻燈』の聴き方とリンクする部分があるように感じました。
特に、アナログ的な音楽体験を現代的な方法で再現し、
絵画を「読み取る」ことで音楽を聴くという斬新なアプローチが重なります。
また、
小説の中で
「保存・保管」の重要性
が語られている点も、
幻燈アルバムの冒頭と通じるように思えます。
つまり、
ヨルシカの楽曲『451』では、「燃やす」という破壊的なテーマが歌詞に表現されていますが、
その裏には「保管・保存」という相反する側面も
隠されているのではないでしょうか。
この二面性こそが、
単なる燃焼ではなく再生の可能性をも示唆している
ように思われます。
この点は、
「月に吠える」の考察で触れた
「腐敗、死を経たのちに再生する」
というニュアンスとも共通しています。
燃やすことで一旦失われたものが、
新たに生まれ変わるというような「循環」であり、
いわば「循環させる」という意図
があるような気がしました。
これが『451』の歌詞やテーマに含まれているメッセージの核心なのではないかと思いました。
華氏451度 [新訳版]
著者 レイ・ブラッドベリ
訳者 伊藤典夫
発行所 株式会社早川書房
P261
「人は死ぬとき、なにかを残していかねばならない、と祖父はいっていた。子どもでも、本でも、絵でも、家でも、自作の塀でも、手づくりの靴でもいい。草花を植えた庭でもいい。なにか、死んだときに魂の行き場所になるような、なんらかのかたちで手をかけたものを残すのだ。そうすれば、誰かがお前が植えた樹や花を見れば、お前はそこにいることになる。なにをしてもいい、と祖父はいっていたな。お前が手をふれる前の姿とはちがうものに、お前が手を放したあともお前らしさが残っているものに変えることができれば、なにをしてもいいと。ただ芝を刈るだけの人間と、庭師とのちがいは、ものにどうふれるかのちがいだ、ともいっていた。芝を刈るだけの人間はそこにいないも同然だが、庭師は終生、そこに存在する、とね」
この部分は、
ヨルシカの「盗作」に近い考え方を反映しているようにも感じられます。
(ライブを直接見ていないので断言はできませんが)
「残す」ということの意味は、
単なる保管や保存にとどまりません。
むしろ、自分が手を加えたものを通じて、
「魂の行き場所」を作るという深い意義を持っていると解釈できます。
ただ存在を記録するだけではなく、
自らが触れることで形を変え、そこに「自分らしさ」を宿す。
これが、本当の意味で「残す」という行為なのでしょう。
残した先にある、「次」を念頭に置いている、そんな気がしました。
また、彼は映画『白鯨』の脚本も手掛けた作家で、多読家として知られ、数多くの作品を生み出してきました。
この背景は、後ほど触れる「白鯨」の考察部分でも重要なリンクを形成するかもしれません。
どうでしょうかね。
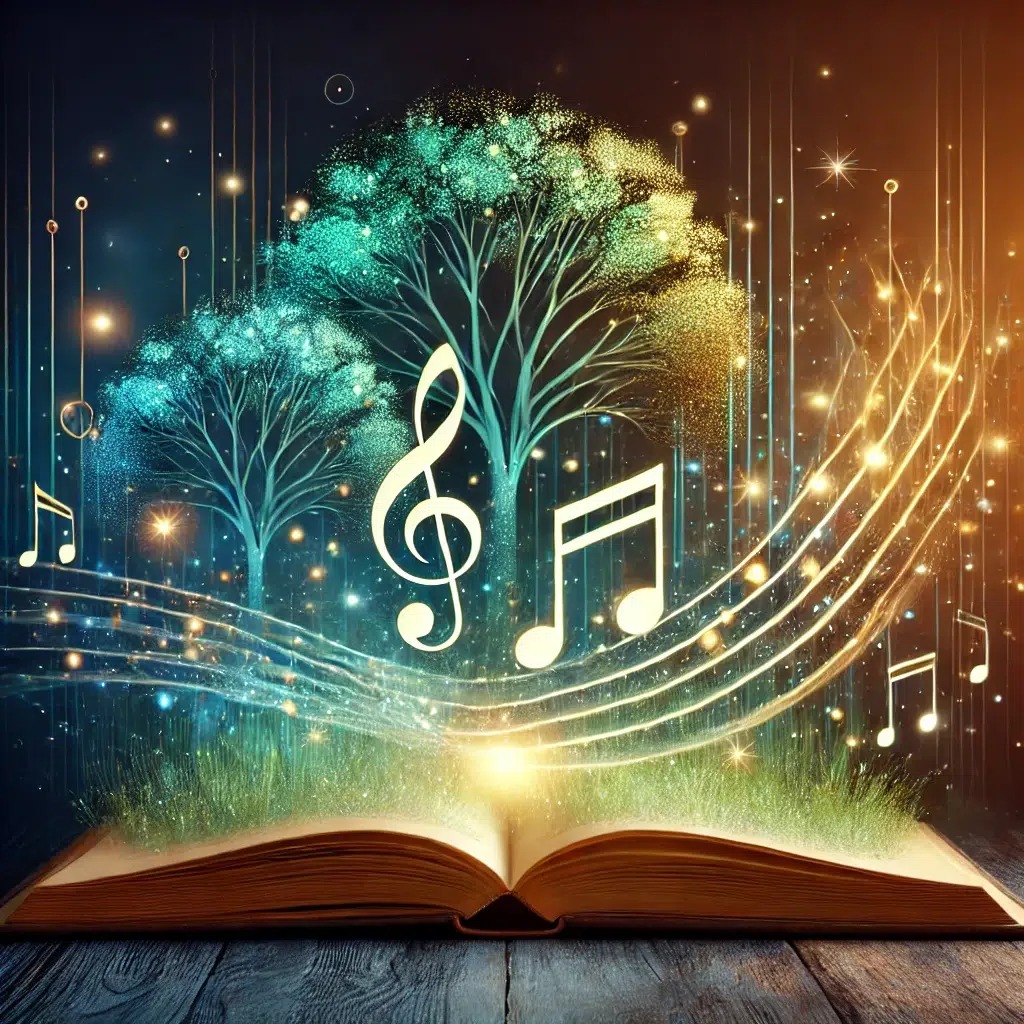 音楽と考察の森 ”Groval of Global”
音楽と考察の森 ”Groval of Global”