最後に、「アルジャーノン」です。
長かった記事もこれで終わります。
アルジャーノンは、原作を読み、そのテキストとストーリーに驚き、感動しました。
ある意味、シュタインズゲートというゲームを思い出しました。
論理に従って、
先がどうなっていくかがおぼろげに予想できつつ、
見守っていくような作品として同じ印象を持ちました。
すごい。
ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』─(A⇔Ā)=Aの世界─
藤田裕司
https://opac-ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/webopac/TD00001561
P8
つまり、作者キイスは、プラトンの「洞窟の比喩」(仏教流に「端的にいえば〈上求菩提・下化衆生〉の教説)をベースにして、チャーリィが体験した宇宙への「膨張」と地上への「縮小」という往復運動を、長年、洞窟の中で暮らしてきた人間が太陽の方に向かって上昇し、その後、下降して元の洞窟に戻るという体験と、重ね合わせているわけである。それは、チャーリィが1年足らずのうちに体験したIQの急速な上昇及び下降とパラレルなこと、いうまでもない。
P9
チャーリーの場合、魂の一部をなす知性(理知)は大いに向上するものの、その器たる肉体をめぐって新旧のチャーリィが確執を起こし、しばしば体外離脱や二重身ないし二重人格様の体験が生じる、という問題を呈している。
P9
しかし、まもなくチャーリィの退行が始まり、その過程で上記のようにアリスと結ばれたとき、二人は「人間の魂を再生し永遠不滅のものとするために合体」し、チャーリィの「肉体は宇宙の広大な海に呑みこまれ、不思議な洗礼をほどこされ」た、と述べられている。
P10
彼の詳細な「経過報告」が示しているように、実は彼がIQの上昇によって可能としたのは、単に過去のトラウマ的体験の想起だけでなく、それにまつわる感情の自己認識、すなわちメタ認知であった。
P11
つまり、チャーリィの自我が目覚めたのである。目覚めた自我は、それまで埋没していた周りの集団に対して自らの存在をアピールし、個としての自立の承認を得ようとする。
P11
この「融合」体験は、また「没我」的と形容してもよい。「我」を‘something great’に「没」するからである。
P11
しかし、「我」前の「没我」と「我」後のそれとでは、同じ「没我」でも、いわば次元が異なる。「我」後の「没我」は、「我」と「我」前の「没我」との二元相対を脱した、すなわち、「没我」かそうでないかということさえ問題にならない、一元的・絶対的な「没我」である。いいかえれば、「我」も「没我」も包んで越えた、高次の「没我」であって、例の「神秘」的な「融合」体験がその転機となっている。
P12
それは、チャーリィが、その気になれば元のドナー・ベイカリーで以前のような暮らしができたであろうにもかかわらず、あえてそうせずに、なぜ、ひとりウォレン養護学校に身を引いていったのか、ということについてである。(中略)これからニルヴァーナの境に入る彼には、それにふさわしい〈あの世〉が必要であったからだ、と。
この論文を読んで、深く納得しました。
特に「没我」から「我」が生まれ、
しだいに「没我」へと戻っていくところが単なる原点回帰ではなく、
新しい自分に変わっていくというニュアンスがあることを知り、
本当に物語の読み取りや深い理解というものが、
自分にはまだ不足していると気づかされました。
同じであるはずが、なかったのです。
さらに、死にゆく姿であっても、
それが終わりを迎えると同時に、
次、つまり来世を見据えているという意味合いもこの物語には込められていることを知りました。
この「幻燈」というアルバムにおいて、
何度も繰り返される
「終わりからの再生」
というテーマが、やはりアルバムの最後を締めくくる楽曲にもしっかりと反映されていました。
この楽曲が「幻燈」というアルバムに存在する意味を考えます。
この「アルジャーノン」の歌詞においてこの視点は、
要は二段階を経た「没我」の状態にある自分であり、
もう間もなく死んでいくところを描いています。
しかし
同時に「没後」の自分から分離をした自分が生まれており、
死にゆく自分から離れ、「我」を持っていく様を見守っています。
その離れていく自分は、
結果としては同じように、
「我」を持ったあと、
「没我」となり死んでいく。
しかし、
また別の自分が生まれ「我」を持って自分から離れていくというような、
輪廻転生をしている様が表現されていると思います。
それは、歌詞のなかに「いつか」(アルジャーノンの歌詞より引用)という文言があります。
それは、輪廻転生を繰り返す中でも、
同じ死を迎える結果は同じでも、
まったく同じ状態に戻っているわけではなく、
いうなれば少しずつではあれども、
より「高次」であり「没我」の自分となって死んでいくこと
を繰り返している
ので、
純粋な円環ではないということから、
最終的には異なる結果を目指していることがその三文字に表されていると思います。
長い迷路の先に、
「追いつけない人に出会う」
(アルジャーノンの歌詞より引用)
というゴールを祈っていることかなと読み取りました。
当初、この『幻燈』の楽曲たちは、作り手の好みで生まれたものであり、特に深い関連性はなく、単に楽曲が並んでいるだけだと思っていました。
しかし、考察を進める中で、このアルバム全体にテーマが存在していると思いました。
それが、「非現実である幻想を創作する」と「終わりからの再生」という二つの意図です。
この二つの意図を捉えることで、『幻燈』が単なる楽曲の集合体ではなく、有機的で意図を持った楽曲群であると喩えようと思いました。
この意図を掘り下げるにあたり、「ミクロな視点」と「マクロな視点」の二つの観点で分けて考えることが有効だと感じました。
まず、「幻燈」におけるミクロな視点でいうと、「非現実である幻想を創作する」です。
これは、考察をすすめた結果、画家が存在しない幻想を創作している点で、MVなどで描かれている女性は今世では存在していないということです。
それは月と猫のダンスの意図にもかかわってくるかと思いますが、
ヨルシカの物語における輪廻転生において、人間同士で出会えるわけではなく、
動物として出会う意味合いも考えると、
今回の「幻燈」の主人公である画家はなにかしらの事情で女性には会えず、
一生を終えることとなる。
しかし、前世からの記憶により、なぜか頭の中にある女性を描く。
それは幻想であり、存在はしていないけれど、なぜかその幻想に心惹かれ、キャンパスに描いてしまうと解釈してみました。
つぎに、「幻燈」におけるマクロな視点、「終わりからの再生」です。
これを考えるには、まず「玄冬」という言葉を踏まえる必要があります。
この言葉は、ブログ記事を書く前から耳にしていたため、アルバム全体に冬という意味合いが込められているのではないかと感じていました。
実際、このアルバム全体には「終わりを迎える冬」のニュアンスが漂っています。
それを踏まえると、
ヨルシカはこの『幻燈』をもってそもそも物語の「終わり」を迎えさせようとしているのではないか、
と一見すると感じられるのです。
例えば、最終楽曲である「アルジャーノン」を考察していた際に感じましたが、
ヨルシカのアルバムリリースは「アルジャーノン」の物語に似た流れを辿っています。
『夏草が邪魔をする』や『負け犬にアンコールはいらない』といったアルバムは、『だから僕は音楽を辞めた』と『エルマ』という二つのコンセプトアルバムを補完する役割を持っています。
この4つのアルバムが表現しているのは、「青春」と「朱夏」という二つの季節の移ろいです。
その後、『盗作』では「白秋」の季節を迎えます。
このアルバム内で「青春」や「朱夏」の曲名が引用されているのは、
これらの季節を経て「白秋」に至ったことを示しているのでしょう。
『盗作』ではこれまでの功績を否定し、
これ以上の成長を自ら止めようとする音楽泥棒の姿が描かれておりますが、
これが比喩のように感じました。
これが「終わり」へとゆっくり向かう兆しであることを感じさせます。
そして『幻燈』です。
このアルバムは「玄冬」、すなわち老いと死を迎える季節を象徴しています。
一見すると、この作品により、物語自体の終焉を描こうとしているようにも思えます。
しかし、違います。
『幻燈』は単に「終わり」を描こうとしたアルバムではなく、その核心には「終わりからの再生」というテーマを持っています。
『幻燈』を作り上げたことで、ヨルシカは単に物語を終わらせるのではなく、
新たなステージ、
輪廻転生の新たな周回へ向かおうとさせている、
そういう風に感じました。
このアルバムは「冬」でありながら、
次の「春」を迎えるためという「目覚め」
をするために必要とした作品なのです。
その意味で、「冬眠」の意味合いがあるかもしれません。
このように
二つの視点があると考えると面白いかなと、
創作的に喩えてみました。
【さいごに】:解放感はひとしお
いやーーーー、長い。長すぎる。
やっと出来上がりましたが、まだ書ききれていない内容もあるので、補足として書こうと思います。
本当にがんばりました。
長すぎでここまで読める人は本当にわずかかなと思います。
でも読めた方には、ぜひあなたが感じた『幻燈』の魅力など教えてくださいな。
お読みいただきありがとうございました。
そんでは。
どどり
以下は記事中の参考文献を載せさせていただきました。
このブログ記事を書くためには、この参考文献がなければ不可能でした。
モチーフとなっているこのは小説とされてますが、いわば芸術作品の意図を読み取り、理解することは僕のようなものには困難です。あまりにも時間がなく、また何年もかけて磨かれたものがないとたどり着けない文章ばかりでした。
本当に感謝申し上げます、ありがとうございました。
感謝
参考文献まとめ
都落ち
①万葉集ナビ
https://manyoshu-japan.com/13462
https://manyoshu-japan.com/13464/
https://manyoshu-japan.com/13463/
②「朝川渡る」試解
小島恵子
https://kdu.repo.nii.ac.jp/record/866/files/KJ00004726250.pdf
チノカテ
①アンドレ・ジッドの『地の糧』
成谷麻理子
https://waseda.repo.nii.ac.jp/records/1777
雪国
①〈論文〉川端康成 『雪國』 読解試論―「鏡」の世界をめぐって―
河村民部
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/7970
月に吠える
①
萩原朔太郎「月に吠える」の思想と方法
長野隆
https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/records/2026
451
①華氏451度 [新訳版]
著者 レイ・ブラッドベリ
訳者 伊藤典夫
発行所 株式会社早川書房
パドドゥ
①芥川龍之介作「舞踏会」考證 : ピエル・ロティ作「江戸の舞踏会」(Un Bal á Yeddo)との比較
大西忠雄
https://opac.tenri-u.ac.jp/repo/repository/metadata/363
②「舞踏会」におけるロティとヴァトーの位相
島内裕子
https://ouj.repo.nii.ac.jp/records/7354
③つかのまのユートピアとしての雅宴画とその系譜
吉田朋子
https://notredame.repo.nii.ac.jp/records/602
又三郎
「風野又三郎から風の又三郎へ」部分より引用
https://tokyoaccent.com/kazeno/karahe.html
②遠くからきた少年 ー宮沢賢治「風の又三郎」をめぐってー
川島秀一
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yeiwa/1/0/1_KJ00004746124/_article/-char/ja
③ヨルシカ 又三郎特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/yorushika/matasaburou
靴の花火
①宮沢賢治童話絵本の研究 : 「よだかの星」の場合
木村東吉
https://cur-ren.repo.nii.ac.jp/records/765
②宮沢賢治「よだかの星」(<特集>文学教材研究)
太田正夫
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/14/1/14_KJ00010058185/_article/-char/ja
③よだかの星
宮沢賢治
青空文庫
https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/473_42318.html
老人と海
①『老人と海』におけるヘミングウエイの自然 : その二重性とエマソン的自然観
梅沢時子
http://repository.tokaigakuen-u.ac.jp/dspace/handle/11334/1119
さよならモルテン
①『ニルスのふしぎな旅』におけるスウェーデンの近代化とセルマ・ラーゲルレーヴの国家観
日本児童文学学会例会(プロジェクト人魚第14 回研究会)
中丸 禎子
https://www7b.biglobe.ne.jp/~nakamaru_teiko/pdf/nils.2014.pdf
作者 セルマ・ラーゲルレーヴ
訳者 菱木晃子
発行 株式会社福音館書店
いさな
①『白鯨』研究 ―物語世界と共鳴する音表現の諸相
濱田みゆき
https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/2000015
左右盲
①オスカー・ワイルド「幸福な王子」 ――唯美主義運動の〈使者〉としてのツバメ――
輪湖美帆
https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/6812
アルジャーノン
①ダニエル・キイス『アルジャーノンに花束を』─(A⇔Ā)=Aの世界─
藤田裕司
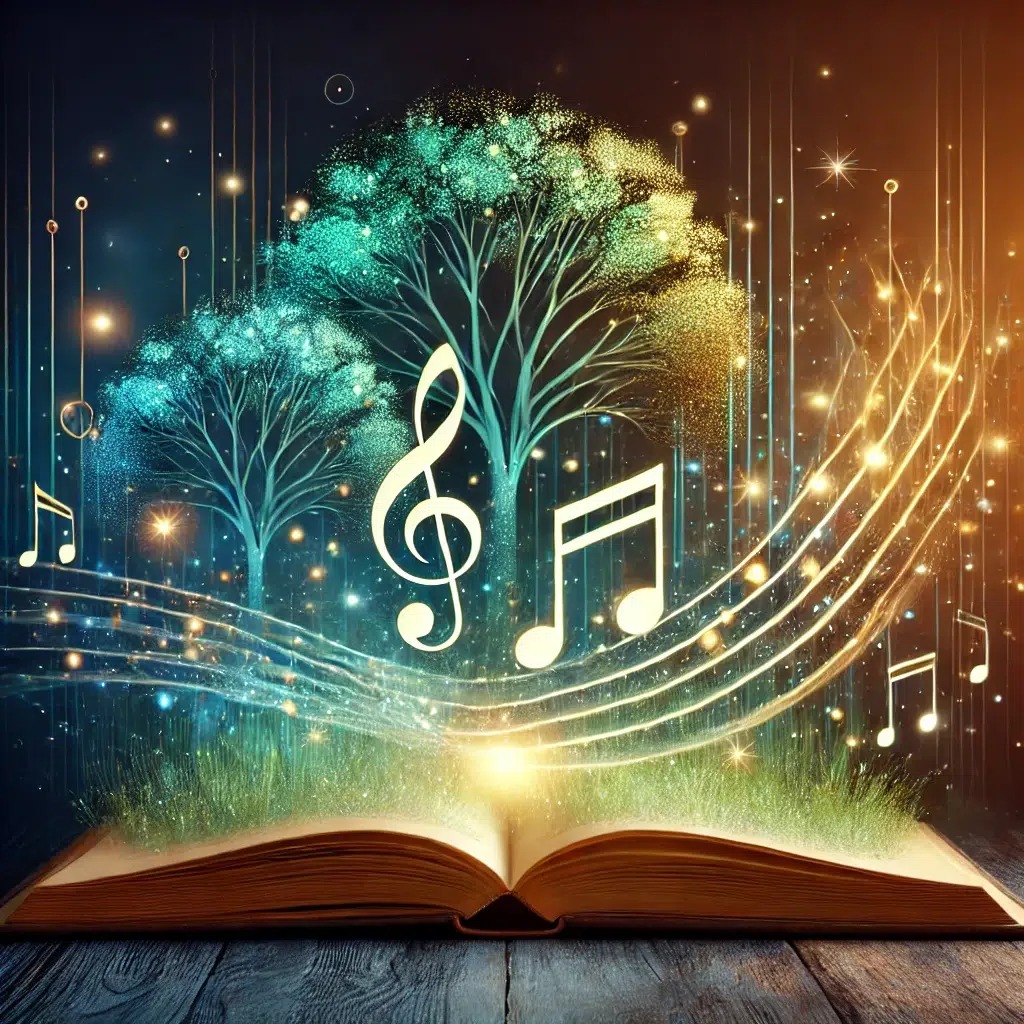 音楽と考察の森 ”Groval of Global”
音楽と考察の森 ”Groval of Global” 








